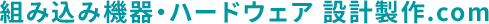設計のポイント
FPGA設計のポイント
- verilog記述のポイント:always内の出力はできる限り少なくする
- 定数のビット幅明示
- FPGAによるスキャンコンバータの実装
- ストリーミングデータ参照による高速演算処理
- FPGAによるLCDコントローラの実装
- USB HS FIFOによる高速計測アプリケーションの実装
- verilog記述のポイント:連接演算子を使う
- verilog記述のポイント:複雑な組み合わせ回路にfunctionを使用する
- verilog記述のポイント:wireとregの違い
- verilog記述のポイント:双方向ピン(inout)を使用する
- verilog記述のポイント:モジュールの接続
- verilog記述のポイント:output regを使用する
- verilog記述のポイント:定数にparameterを使う
- verilog記述のポイント:二次元配列
- verilog記述のポイント:ブロッキング・ノンブロッキング
- DCFIFOによりクロックが異なる回路を接続し、開発リードタイム短縮
- PC搭載システムのダウンサイジング
- 複数のSPIデバイスの同時制御
- ソフトコアプロセッサ使用によるマイコンとゲートアレイのワンチップ化
- FPGA利用によるCPU負荷の削減
マイコン開発のポイント
- LEDを使用したデバッグ
- MRAMを使用して高頻度書き込みを必要とするアプリケーションの実装
- I/Oエクスパンダ使用による入出力点数の拡張
- 7セグメントLEDのダイナミック点灯でI/O点数の削減
- マイコン制御による制御盤の小型化とコスト低減
- 期待通りの動きをしない場合のマイコンチェックのポイント:未使用端子の適切な処理
- 期待通りの動きをしない場合のマイコンチェックのポイント:電流過多の原因
- 期待通りの動作をしない場合のマイコンチェックのポイント:ビットレートを合わせる
- 優先レベルの設定で、多重割り込み時の正常動作を確保
- 割り込み動作の短時間化で動作レスポンス向上
- DMACを利用したCAN通信で高頻度通信を実現
組み込み機器 基本設計のポイント
RaspberryPi活用のポイント
- 赤外線リモコンの使用
- spidevを使用する
- 組み込み機器に簡易GUIを採用する
- RaspberryPiを用いて情報表示板を製作する
- spiのバッファサイズを変更する
- RaspberryPiでシャットダウンフリー化を実現
- RaspberryPiをPLC通信アダプタとして使う
- RaspberryPi OSにて日本語を使用する